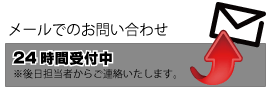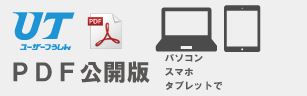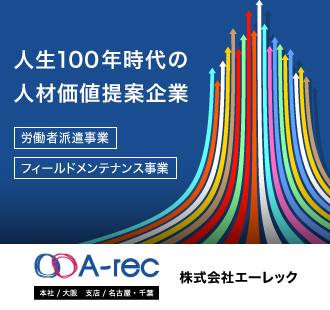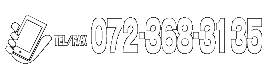愛知産業 ハームレ社5軸MC販売20周年記念講演を開催

ドイツ・日本ユーザー各社がリアルに語った核心
「多品種少ロット生産の自動化を必要とする中小企業の成功事例」
愛知産業(本社=東京都品川区)が2004年から開始したドイツ・HERMLE(ハームレ)社のマシニングセンタ販売事業が20周年の節目を迎え、ハームレ販売20周年記念イベントとして、MCのユーザーを国内外から招いた記念講演を、昨年12月5日に東京・品川区の大崎ブライトコアホールで開催した。
世界一のオートメーションを最大活用しているドイツ・日本ユーザーのキーパーソン、中でも、多品種少ロット生産の自動化を必要としている中小企業の成功事例が紹介され、参加者らにとっては「多品種少ロットの自動化」をより身近に感じ、次なる技術導入への出発点となった。愛知産業は、1936(昭和11)年に金属加工分野において接合技術および冶金技術の事業からスタートし、当時の日本市場には存在しない接合技術や溶接装置を海外から習得し、戦前・戦後において日本の工業課題に応えてきた。
「ハームレ社独自技術の自動化導入企業は、事業継続と成長を実現している」(愛知産業 井上博貴社長)
開会のあいさつに立った愛知産業の井上博貴社長は、「20年前、ほんの小さなお客様の特殊なニーズがきっかけでハームレ社の製品に出会い、その5軸MCの設計思想や堅牢性に惚れ込み、ぜひ日本で販売したいという強い思いから、1名の営業マンと1名のサービスマンで新たな事業を立ち上げた。当社は工作機械のレトロフィット制御改造をしていたこともあり、新事業の立ち上がりをスムーズに展開することができた」と述懐した。
さらに、日本は今、人手不足や後継者不足など多くの課題を抱える中で、「私も欧州・米国の企業との交流から、この先のものづくりにおいて省力化・自動化が欠かせない解決策であるとの強い思いを持っている。当社は省資源、省エネ、省力化に役立つことを使命とする会社だ」とし、「ハームレ社は、まさにこれから先のモノづくりを見据えて独自技術の自動化を提案し、その技術を導入した企業は事業の継続と成長を実現している」と続けた。
井上社長はこの様子を自身の目で見て、「これは実際に日本のお客様にもぜひ紹介したい」との強い思いから、ハームレ社最新の省力化・自動化技術を採用しているドイツおよび日本のユーザーの声を中心に、多品種少量ロット生産の自動化技術をテーマとした記念セミナーの開催に至ったと説明した。
続いて、ドイツ大使館、ドイツ機械工業連盟日本代表事務所から、「商習慣など日本特有の壁がある」等にふれながらの来賓祝辞のあと、次のプログラム4本が順に講演された。
①ハームレ(HERMLE AG)社『ハームレが開発に注力する超フレキシブルな自動化システムとソフトウエア』②【ドイツユーザー】コンドールグループ(Condor Customs Solutions GmbH & Co.KG)『将来を見据え導入した多品種少ロット生産の自動化システムの活用法』③【国内ユーザー】吉川製作所『既存機の自動化からスタートした自動化システム導入の背景』④ラング(LANG Technik GmbH)社『クランプ製品から広がる自動化システムの進化と最新情報』。
「愛知産業は何度もハームレにインスピレーションを与えてきた信頼、日本マーケット開拓の協力関係を象徴」(ハームレ社 ミハエル・ビッサー営業本部長)
①ハームレ営業本部長のミハエル・ビッサー氏が、ハームレ社の概要、歴史、工場(ツィマーンに新工場開設など)、構造原理(ミネラルキャスティングにおける改良型ガントリー設計など)、製品(ハームレ パフォーマンスラインとハイパフォーマンスライン、自動化ソリューションなど)を紹介。このうち、日本初のハームレユーザーについて、1号機としてハームレ「C40」を納入~現在の国内ユーザー納入状況・所在地にふれ、「愛知産業とハームレの組み合わせは、国内マーケット開拓の強力なビジネスを象徴するだけでなく、過去20年にわたって何度も私たちにインスピレーションを与えてきた信頼と友好的な協力関係を象徴している」と感謝の念を添えた。
「ロボットを仲間だと思うオープンな心を」
②では、ドイツ・東ウェストファリアのザルツコッテンに立地し、医療機器の開発・販売、製造、金属およびプラスチック加工を手掛けるコンドール社のドミニク・シュルテ氏が、ドイツの生産拠点での厳しい状況(熟練労働者の不足、2交代制や3交代制で働く意欲のある従業員の減少など)にふれながら、回転テーブルを搭載したハームレ「C32」2台、部品・パレットを搬送する自動化ソリューションとしてロボット「RS01」の導入といった「ハームレを活用した自動化への投資」を解決策として示した。
その上で、ハームレを選ぶ理由として、「切削加工と自動化をワンストップで実現し、夜間シフトや週末勤務なしで24時間365日の生産が可能な一貫した自動化ソリューション」と挙げ、「2022年にハームレのソリューションを導入して以来、すでに1800以上のプログラムの作成実績がある」とも付け加えた。さらには、自動化を進める前の準備について、「ロボットを仲間だと思って、オープンな心を持つこと」だと説いた。
休憩を挟んでの③では、島根県出雲市に所在する吉川製作所の吉川浩輔専務が、自動化のステップとして、大量生産、長時間加工品、多品種生産品に分類し解説した。2017年のLANG20面パレット購入での愛知産業との縁を機に、翌18年にハームレ「C42UMT」、23年には「C650」を設備した。ハームレ社MC導入を考え始めてからの「11間が無駄だった」と言わしめるほど、先行導入済みだった複数の国内他社製MCに比べ「切削工具の刃持ち(耐久性)が違う」と吉川専務は断言する。
そんな中、ハームレ「C650」+3面パレットチェンジャーについては、「まだまだ能力をフルに発揮できていない」として、多品種少ロット生産への挑戦にも言及した。そして、現状と課題を、「CAMによるプログラム作成と標準化、熟練に頼らない機械加工の実現」、「CAMオペレーターの育成」、「設備投資の費用が大きい」と挙げ、加えて、「設備はこれだけ自動化しているのに、請求書・納品書・日報は手書き(苦笑)なので、情報・データのデジタル化、全員がCAMオペレーターであり、ロボット自動段取り、自動制御加工ができるといった喜び、達成感」を将来の夢として語った。
最後の④では、ラング国際営業責任者のトビアス・ファー氏が、愛知産業が同社にとってアジア初の販売パートナーから今やトップ10パートナーへと深まった両社の関係を、「18年前、日本はラング製品販売を開始した海外市場の一つだったが、お客様は、効率的な切削加工プロセスにおける最適なクランプ技術の重要性をすぐに認識した。結果として、日本は長い間アジア全体で最高の市場となった」とふれた。


▲ハームレ社のミハエル・ビッサー氏 ▲約4時間にわたり4講演を聴講

 ▲ドイツユーザー、コンドール社のドミニク・シュルテ氏 ▲日本ユーザー、吉川製作所の吉川浩輔氏
▲ドイツユーザー、コンドール社のドミニク・シュルテ氏 ▲日本ユーザー、吉川製作所の吉川浩輔氏
2025年1月21日